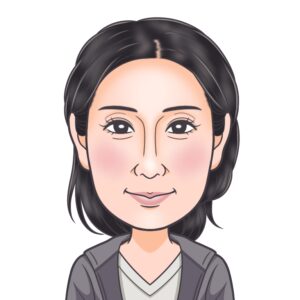親や祖父母が亡くなったあと、「田舎の土地を相続してしまって困っている」という声は少なくありません。
都会の駅近であればすぐに売却できますが、山林や原野などの不便な土地では、買い手がつかず困るケースが多いのが現実です。
維持費や固定資産税の負担もあり、自分の代で処分しておきたいと考える人は増えています。
そんな中、2023年4月にスタートした「相続土地国庫帰属制度」が注目されていますが、果たして本当に使いやすい制度なのでしょうか?
この記事では、相続した不要な土地の対処法と、制度の仕組み・注意点について、わかりやすく解説します。
Contents
いらない土地は売れるのか?まずは相場と販路をチェック
相続した土地が「本当に売れない」のか、まずは調査と行動を起こしてみましょう。
【1】相場の確認
- 国土交通省の「土地総合情報システム」で近隣の取引価格を確認
- 不動産業者に簡易査定を依頼してもOK
【2】販路の工夫
- 一般媒介契約で複数社に売却依頼する
- 自治体の「空き家バンク」に登録する(空き地も掲載可)
- SNSや地域掲示板を活用して個人売買の可能性を探る
それでも難しければ、売却以外の方法を検討します。
【体験談】
筆者の知人も、田舎にある土地の処分に何年も悩んでいました。
不動産会社や空き家バンクに依頼しても買い手も貰い手も見つからず、精神的にも参っていたそうです。
ところがある日、親戚から「必要になったから引き取りたい」と連絡があり、無償で土地を譲ることができたのだとか。
売却益こそなかったものの、「諦めずに待っていたらこんな展開もある」と語ってくれました。
売れない土地の処分方法 4つの選択肢
売れない土地の処分方法には以下の4つがあります。
1. 国庫帰属制度を利用して、国に引き取ってもらう
2. 親族や他者に無償譲渡する
3. 自治体などに寄付する(ただし受け入れられにくい)
4. 相続放棄をする(他の財産も放棄になる)
どの方法も一長一短があり、法的な手続きや費用が伴うことが多いため、事前に専門家(司法書士・税理士・不動産業者)へ相談しましょう。
この記事では、特に注目されている「国庫帰属制度」について詳しく見ていきます。
相続土地国庫帰属制度とは?制度の概要と使える条件
相続土地国庫帰属制度とは、2023年4月に施行された新制度で、一定の条件を満たした不要な土地を、審査・負担金を経て国に引き渡すことができる仕組みです。
以下に、メリット・申請条件・必要費用を箇条書きでまとめましたので参考にしてください。
【メリット】
- 数十年前に相続した土地でも申請可能
- 宅地だけでなく、農地や山林なども対象
- 引き取り後は税金・管理責任がゼロになる
【申請条件】(一部抜粋)
- 相続などにより取得した土地であること
- 建物や担保権が設定されていない
- 他人が使っていない土地であること
- 境界が明確で、争いがない
【必要費用】
制度の利用には、以下の手続きと費用がかかります。
- 審査手数料:1筆あたり14,000円
- 負担金:原則20万円(土地によって増減)
尚、申請から引き取り決定までは数カ月以上かかるケースもあり、専門家(司法書士・不動産鑑定士など)に相談するのが安心です。
申請フローや詳しい条件は法務省の特設ページをご確認ください。
スポンサーリンク
注意!このような土地は引き取ってもらえない
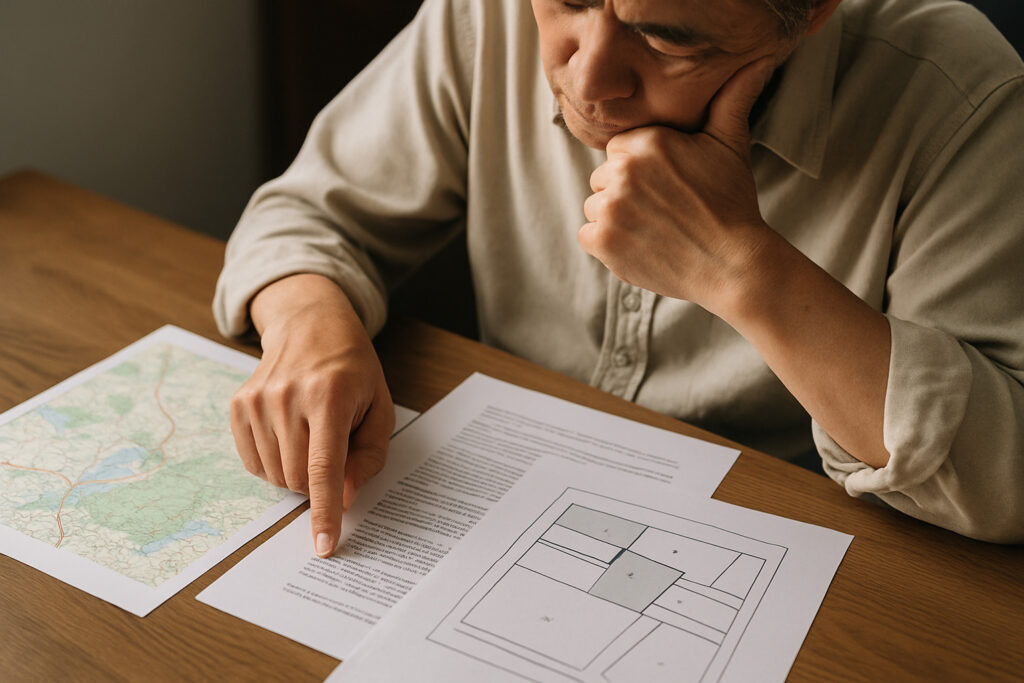
制度には「却下要件」「不承認要件」が細かく定められており、条件をクリアできなければ申請が通りません。
【主な却下例】
- 建物が残っている
- 通路・墓地・ため池などが含まれる
- 権利関係(担保権、借地など)が複雑
- 境界不明・争いがある土地
【主な不承認例】
- 崖地など管理に大きな費用がかかる土地
- 地中に埋設物がある
- 隣人との通行トラブルがある
- 鳥獣・害虫による被害が生じている土地
特に「境界不明」「通路・墓地付き」などの条件は田舎の土地に多く、制度を使えないケースがあるので注意しましょう。

まとめ いらない土地こそ、早めの対策がカギ
相続した土地が「不要」「売れない」と感じたら、放置せずに早めの整理・対策が重要です。
国庫帰属制度は「使える人にはありがたい制度」ですが、費用も手間もかかり、条件も厳しめ。
「いずれ困るなら、今行動する」 「専門家に評価・調査してもらう」
そういった一歩が、将来の相続トラブルや子ども世代の負担を軽くしてくれます。