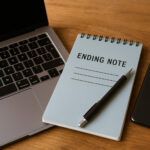「タンス預金」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
タンス預金とは、現金を銀行などに預けず自宅で保管することです。
もちろんタンスに限ったことではなく、自宅内のどこに保管していてもタンス預金といわれます。
相続税対策として現金を自宅にこっそり保管している人もいるかもしれませんね。
近年、相続税対策としてタンス預金を検討する方が増えていますが、国税庁はこうした動きに敏感に対応しています。
特に2024年7月の新紙幣発行を機に、現金による資産隠しはますます「発覚しやすく」なってきています。
「親が多額の現金を自宅で保管していた」「亡くなった後、どこに保管されていたか分からず困った」というような声も聞かれます。
相続の場面でトラブルにならないためにも、タンス預金に潜むリスクと現実を理解しておきましょう。
タンス預金はいずれバレる可能性が高いのです!
この記事では、タンス預金のデメリット、そして税務調査でタンス預金がバレる理由について解説していきます。
Contents
日本のタンス預金合計額とタンス預金をする理由とは?
日本中のタンス預金の合計額は、なんと、30兆~80兆もあるといわれています。
タンス預金は、銀行口座が凍結された際や銀行破綻時の保険として役に立つ場合があります。
また、緊急でお金が必要になった時のために、手元にいくらかお金があれば安心だと考える人もいるでしょう。
そのため、中高年を始めとする多くの人々がタンス預金をしているのです。
タンス預金が少額なのであれば、万が一のときの緊急対応用として良いのかもしれません。
しかし、タンス預金をする人の中には、「収入を隠して相続税を少なく済まそう」と企む人がいて問題になっています。

タンス預金のリスクとデメリット4選
タンス預金は、便利な反面、多くのデメリットがあります。
そこでタンス預金の代表的なデメリットについて、以下に解説していきます!
申告漏れでペナルティが課せられる
タンス預金は、持ち主が亡くなった場合、相続税の課税対象となります。
しかし、「税務署に申告しなければバレない」との勝手な理由をつけて、タンス預金を隠してしまう人が世の中には存在します。
タンス預金を隠したことが税務署にばれると、大きなペナルティが課されることとなるので注意が必要です。
※ペナルティの内容については後述します。
盗難のリスクがある
現在の日本では、詐欺や犯罪が横行しています。
「盗難」もそのうちのひとつです。
私の友人は、昔、自宅マンションに強盗が入り、腕時計や宝飾品をごっそりと盗まれました。
強盗は、常日頃から友人が出勤中などで留守にする時間帯を調査していた模様。
鍵をどうやって開けたのか分かりませんが、警察の人曰く、外国のプロ窃盗団の仕業ではないかとのこと。
20年がたった今でも、犯人は捕まっていないそうです。
詐欺や犯罪は日に日に巧妙化してきています。
自宅に大金を保管することは、大変危険だと思ったほうが良いでしょう。
災害のリスクがある
これも私の友人の話です。
友人のマンションで、隣の部屋の住民が火事を起こしました。
隣の部屋から煙がもくもくと入ってきて、命に危険を感じた友人は慌てて外に避難しました。
幸いなことに友人の部屋には煙以外の被害はありませんでしたが、火事を起こした部屋は大惨事‼
運が悪ければ友人の部屋も燃えてしまっていたかもしれません。
自分が日ごろ気を付けていたとしても、急に起こるのが「災害」というもの。
火事や水害などに巻き込まれると、大金は一瞬で消えてしまいます。
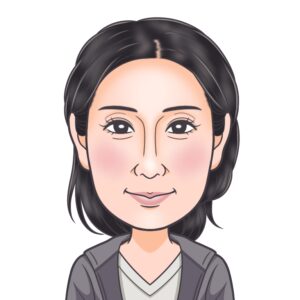

利息がつかない
銀行に預けていても利息がほとんど付かないという理由で、自宅に現金を保管している人もいるかもしれません。
しかし、定期預金の利息は上がりましたし、株や投資で運用すれば配当や利息を手にすることもできます。
タンス預金をしているだけでは、これらのメリットを享受することができません。
タンス預金が税務調査などでバレる理由

冒頭に書きました通り、タンス預金はいずれバレます!
その理由を説明していきます。
タンス預金がバレる理由① 財産を把握されている
国民ひとりひとりの収入や財産は国から把握されているのはご存じですか?
2001年から運用が開始された「国税総合管理(KSK)システム」で全て分かってしまうのです。
個々人の「確定申告」や「源泉徴収票」などにより収入の情報を入手しています。
タンス預金がバレる理由② 預金通帳などのチェックが入る
税務調査員は、申告額とKSKシステムの突合の結果、亡くなった人の過去の預金通帳のチェックを行います。
銀行の取引記録を納税者の同意なく勝手に見ることができ、過去10年に遡って調べられます。
重点的に調査されるのが現金の引き出しです。(亡くなった人だけではなく相続人の預金通帳もチェックしています。)
また、通帳だけでなく、「反面調査」といって取引銀行・生命保険会社などの金融機関から情報を聞き出す場合もあるそうです。
タンス預金がバレる理由③ 新紙幣発行
2024年7月から新しい紙幣(新一万円札:渋沢栄一、五千円札:津田梅子、千円札:北里柴三郎)が発行される予定です。
新紙幣には最新の偽造防止技術が施される一方で、旧紙幣の流通が徐々に減ることで、タンス預金をしていた人が古い紙幣を使う過程で発覚する可能性が高まります。
特に多額の旧紙幣を金融機関で一気に新札へ交換する場合、金融機関が不審に思い、税務署に情報提供されるケースも想定されます。
これが「新紙幣発行=タンス預金のあぶり出し」と言われている理由です。

スポンサーリンク
税務調査などでタンス預金がバレたときの罰則とは?
タンス預金がバレた時に発生するペナルティは以下の通りです。
いずれも大きな金額です。気を付けましょう!
注意
- 無申告加算税(期限が過ぎた後に自己申告した場合5%、自主的に申告しなかった場合50万円まで15%、それ以上は20%)
- 過少申告加算税(50万円まで10%、それ以上は15%)
- 延滞税(納付期限翌日から2カ月は年7.3%、3か月目からは年14.6%)
- 重加算税(故意に相続財産を隠ぺいした場合、35%~50%)
タンス預金少額の現金管理はOK、ただしリスクを理解する
タンス預金を完全に否定するわけではありません。
災害時や緊急時の備えとして、数万円~数十万円の現金を自宅に保管しておくのは実用的とも言えます。
ただし、火災・盗難・水害などで現金が失われるリスクや、相続時に申告漏れのトラブルに発展する可能性があることは理解しておく必要があります。
また、新紙幣導入に伴う「現金の目立ちやすさ」がある今、自宅に多額の現金を置くことのリスクは以前よりも高まっています。
タンス預金による申告漏れが「うっかり」だったとしても、税務署は厳しい姿勢で調査を行います。
申告漏れが発覚すれば延滞税や加算税が課されるため、家族に迷惑をかける結果にもなりかねません。
近年では、電子マネーや証券口座など「見えるお金」の管理が主流です。
現金にこだわりすぎず、見える資産管理へのシフトも視野に入れておくと安心です。
-

-
参考デジタル遺品とは?相続トラブルと生前整理のポイントを解説!
「デジタル遺品(遺産)」という言葉を最近よく耳にするようになりました。 この言葉には明確な定義まではないそうですが、パソコンやスマホがらみの遺品ということは何となく分かりますよね…? 親が亡くなった後 ...
続きを見る
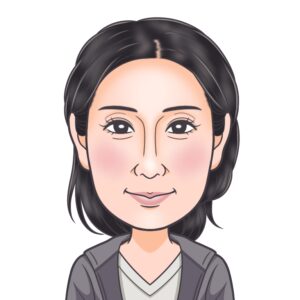
まとめ 相続税対策としてのタンス預金はやめるべき?
タンス預金をしていると、緊急時などに便利だと感じるかもしれません。
もちろん自分の財産ですから、盗難や災害などのデメリットさえ把握していれば、どこで保管しても構いません。
しかし、タンス預金の本当の問題点は、タンス預金の所有者が亡くなった時にタンス預金を相続税の申告書に記載しない人がいるということ。
これは明らかに脱税行為になるので、国や税務署が放っておくわけはありません。
もし、タンス預金の申告漏れが意図的ではなかったとしても、ある程度のペナルティは被ってしまうので、できるだけタンス預金はしないようにしましょう!
最後までお読みいただきありがとうございました。